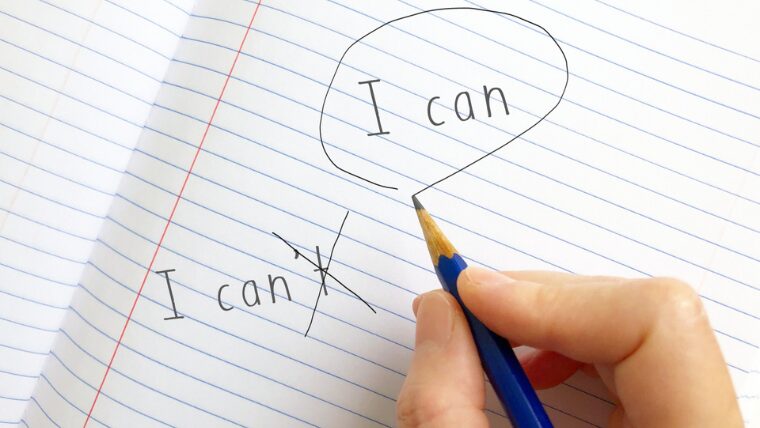女性の厄年

女性にとって「厄年」とは、人生の節目にあたる年齢であり、心身ともに変化が起こりやすい時期とされています。厄年は日本の伝統文化に基づく考え方であり、注意が必要な年齢として広く知られています。本記事では、女性の厄年についての基本情報、厄年における注意点、そして過ごし方のヒントをご紹介します。
女性の厄年とは?
厄年は、体や運気に変化が起こりやすい年齢を指し、昔から「災難に遭いやすい年」と言われています。特に女性の厄年は以下の年齢が挙げられます:
- 前厄:18歳、32歳、36歳
- 本厄:19歳、33歳、37歳
- 後厄:20歳、34歳、38歳
これらの年齢は数え年(生まれた年を1歳とする日本の伝統的な年齢計算法)で数えますが、現在では満年齢を基準に考える場合もあります。
陰陽道における厄年の意味
1. 「厄」の概念
陰陽道では、人生には運気の流れが良くなる時期と停滞する時期があると考えます。
「厄」とは、運気のバランスが乱れやすい年齢を指し、外部からの災厄や内部の体調不良が発生しやすい時期とされています。
この考え方では、人間も自然界の一部であり、星の配置や五行(木・火・土・金・水)のバランスに影響を受けるとされています。
2. 厄年の年齢の設定
厄年とされる年齢は、人生の節目や身体的変化が起こる時期に重なることが多いです。陰陽道では、以下の理由から特定の年齢が厄年とされます:
- 女性の33歳(大厄)
数え年の33は「三三(さんざん)」と読めるため、不吉とされました。また、この年齢は女性にとってホルモンバランスや身体の変化が目立つ時期でもあり、心身の負担が増えやすい年齢と考えられました。 - 男性の42歳(大厄)
「四二(しに)」と読むことができるため、不吉な年齢とされます。この年齢は、社会的責任が増大し、健康面にもリスクが出やすい時期です。
3. 陰陽道に基づく厄除けの方法
陰陽道では、災厄を未然に防ぐための方法として、以下のような行動が推奨されます:
- ① お祓い
陰陽道では厄年に「祓え」の儀式を行い、体や心についた穢れを清めることで、運気を整えます。これが現代の「厄払い」の元になっています。 - ② 縁起物の活用
お守りや御札を持つことで、災厄を遠ざけ、吉を引き寄せる効果があるとされます。 - ③ 身の回りの清浄化
家や職場の掃除を丁寧に行い、環境を整えることで、陰陽のバランスを保つとされています。 - ④ 星祭り(星回りの調整)
星の運行に合わせた祭りを通じて、運気を良い方向に導く行為が行われます。これは現在も一部の寺社で行われています。
陰陽道と現代の考え方の融合
厄年の考え方は、陰陽道の「自然との調和」や「バランス」を重視する思想に基づいていますが、現代ではこれを健康やメンタルケアに応用する動きも見られます。例えば:
- 生活リズムの見直し:陰陽道の「調和」を現代では「健康的なライフスタイル」と捉え、適度な運動や睡眠の確保に焦点を当てます。
- 心のバランスを整える:陰陽道で言う「祓い」は、心理療法やストレス解消の手段としても解釈できます。
厄年について考えるに当たって
厄年の起源である陰陽道の思想は、ただの迷信ではなく、自然や運気に目を向け、人生を調和させるための知恵として捉えられます。現代の生活においても、厄年を心身を整えるタイミングと考え、前向きに活用してみてはいかがでしょうか?
厄年に気をつけたいこと
厄年は身体的、精神的に負担がかかりやすい時期とされるため、以下の点に注意しましょう。
健康面
19歳付近(思春期後期から成人初期)
この時期は、身体が成人へと移行し、ホルモンバランスが安定する過程にあります。しかし、以下のような健康上の変化やリスクが見られることがあります。
起こりやすい健康変化
- 月経関連のトラブル
月経周期がまだ安定しない場合があり、月経不順や月経困難症が起きやすい時期です。特に初経から数年以内の場合、ホルモンの調整が不十分なことが原因となります。 - 鉄欠乏性貧血
月経が定期的に続くことで鉄分が不足しやすくなり、貧血が起こりやすいです。この時期は特に鉄分やビタミンCを意識した食事が重要です。 - ストレスによる体調不良
進学や就職などの環境変化が多く、ストレスが原因で自律神経の乱れや胃腸の不調、睡眠障害が見られることがあります。
対策
- バランスの取れた栄養摂取(鉄分・タンパク質)
- 適度な運動でホルモンバランスを整える
- 定期的に婦人科を受診し、月経トラブルを相談する
33歳付近(妊娠・出産が多い時期)
この時期は、妊娠や出産を経験する女性が多く、ライフイベントが健康に与える影響が大きくなります。また、社会的役割が増えることで心身への負担が大きくなります。
起こりやすい健康変化
- ホルモンバランスの変化
妊娠を計画している場合や出産後、エストロゲンやプロゲステロンといったホルモンの急激な変動が起こります。これにより、産後うつやPMS(月経前症候群)の症状が悪化する場合があります。 - 疲労や慢性疲労
育児や仕事の両立で過労が蓄積し、慢性的な疲労や睡眠不足に陥りやすくなります。 - 骨密度の低下
妊娠・出産や授乳でカルシウムが不足すると、骨密度の低下リスクが高まります。 - 体型や体重の変化
妊娠・出産後に体型が戻りにくくなり、これが生活習慣病やメンタル面への影響を引き起こすことも。
対策
- 栄養補給(特にカルシウム・ビタミンD)
- 十分な休息とストレス管理(家族やパートナーの協力が鍵)
- 適度な運動(骨密度を維持するためのウォーキングや軽い筋トレ)
37歳付近(加齢による変化が始まる時期)
37歳は、卵巣機能の低下が始まり、プレ更年期の兆候が見られることがある時期です。加齢による身体の変化が次第に顕著になります。
起こりやすい健康変化
- 卵巣機能の低下
エストロゲンの分泌が徐々に減少することで、月経不順や排卵障害が起きる場合があります。不妊のリスクも増加します。 - 肌や髪の変化
ホルモンバランスの変化により、肌のハリが失われたり、髪のボリュームが減るといったエイジングサインが現れることがあります。 - 生活習慣病のリスク増加
基礎代謝の低下に伴い、体重増加や高血圧、糖尿病のリスクが高まることがあります。 - メンタルヘルスの問題
更年期の入口ともいえる時期であり、イライラや落ち込み、睡眠障害などの症状が出ることがあります。
対策
- 健康診断で生活習慣病のリスクを早期発見
- 抗酸化作用のある食品(ビタミンE、Cなど)を積極的に摂取
- ストレス解消のための趣味やリラクゼーションの実践
- 早期の婦人科相談(ホルモンバランスに関する検査など)
共通の注意点
- 早めの婦人科受診
月経のトラブルやホルモンバランスの変化を放置せず、専門医に相談しましょう。 - メンタルヘルスケア
ライフイベントによる負担が心身に影響を与えることを自覚し、セルフケアやカウンセリングを活用しましょう。 - 生活習慣の見直し
厄年をきっかけに食生活や運動習慣を整えることが、長期的な健康につながります。
人間関係
19歳付近:成長と自立の時期
19歳は、思春期が終わり成人へと成長する時期であり、人間関係にも大きな変化が訪れます。
起こりやすい人間関係の変化
- 親子関係の変化
高校卒業や進学、就職などで親元を離れる場合が多く、親子関係が「依存」から「自立」へと変化します。親の期待との葛藤が生じることもあります。 - 友人関係の変化
学校を卒業すると、環境が変わりこれまでの友人関係が希薄になることがあります。一方で、新しい環境での友人作りも求められ、適応力が試される時期です。 - 恋愛関係の変化
初めての本格的な恋愛を経験することが多い時期です。恋愛に対する価値観が形成されるとともに、失恋や依存など、感情面での試練を経験することもあります。
対応のヒント
- 自分の価値観を大切にし、無理に他人に合わせすぎない
- 親と対話の機会を増やし、自立への理解を深めてもらう
- 信頼できる友人やパートナーを少しずつ見つける
33歳付近:ライフイベントの重なる時期
33歳は、女性のライフイベント(結婚、出産、仕事でのキャリア形成)が重なりやすい時期で、人間関係の変化が最も顕著な時期と言えます。
起こりやすい人間関係の変化
- 夫婦関係の変化
結婚後数年経つと、お互いの価値観や生活習慣の違いが明らかになることがあります。また、子どもがいる場合は育児に追われ、夫婦間のコミュニケーションが減ることも。 - 親子関係の変化
親が高齢化し、親の健康や介護に関する話題が増えます。「親に頼る」立場から「親を支える」立場への転換が始まる時期です。 - 友人関係の変化
結婚や育児、仕事の忙しさから友人との時間が減少し、疎遠になることがあります。一方で、同じ境遇の友人(ママ友など)が増えることも。 - 職場での立場の変化
キャリアの中堅層に差し掛かり、後輩を指導したり責任の重い仕事を任されたりすることが増えます。職場での人間関係にプレッシャーを感じることも。
対応のヒント
- 夫婦間でのコミュニケーションを大切にし、家事や育児を分担する
- 親の健康状態を把握し、早めにサポート体制を考える
- 友人との交流の時間を意識的に作る
- 職場では周囲と協力しつつ、過度な負担を避ける
37歳付近:自己再構築の時期
37歳は、女性としての生き方やキャリア、家庭の在り方などを改めて見直す「自己再構築の時期」とも言えます。この時期は内面的な変化が人間関係にも影響を及ぼします。
起こりやすい人間関係の変化
- 夫婦間での価値観の変化
結婚生活が長くなると、夫婦それぞれの価値観のズレが顕在化する場合があります。「子どもを持つかどうか」「キャリアと家庭のバランス」などの課題が議論のきっかけとなることも。 - 子どもとの関係の変化
子どもが小学生以上になると、子育ての形が「保護者」から「指導者・サポーター」へと変わります。子どもの自立心を尊重することが求められます。 - 親との関係の変化
親の高齢化が進み、健康や介護の問題が現実的な課題となります。このことで、兄弟姉妹間の関係にも影響を与えることがあります。 - 社会的孤立のリスク
子育てや仕事の忙しさで自分の時間が減り、趣味や友人との関係が薄れることで孤独感を抱く場合があります。
対応のヒント
- 自分自身の価値観や生き方を明確にし、夫婦間で共有する
- 子どもの成長に合わせた接し方を学ぶ
- 親のサポート体制を家族全体で話し合う
- 趣味や地域活動を通じて新しい友人を作る
共通の注意点
- 変化を受け入れる姿勢
ライフステージが変わる中で、変化を避けるのではなく、前向きに受け入れることが大切です。 - コミュニケーションを意識する
家族や友人、職場の同僚と意識的にコミュニケーションを図り、信頼関係を築く努力をしましょう。 - 自己ケアを忘れない
忙しい時期ほど、自分自身を大切にする時間を持つことが、人間関係を良好に保つカギとなります。
金銭管理
19歳付近:初めての経済的自立の時期
19歳は、多くの女性が高校卒業後に進学や就職などを経験し、親の援助から部分的に自立し始める時期です。この時期には金銭管理に対する意識が形成され始めます。
金銭管理の変化
- 収入が増える
アルバイトや初めての給料を得ることで、自由に使えるお金が増えます。一方で、無計画な支出が増えることもあります。 - 支出の多様化
学費や交通費、交際費、趣味など、自分で管理する必要がある支出項目が増えます。 - 借金のリスク
クレジットカードや分割払いなどの利用を始める人も多く、金銭感覚の未熟さから返済に苦労するケースも見られます。
対策
- 収入と支出を記録し、家計簿やアプリを活用して管理する習慣をつける
- 必要以上にクレジットカードを利用せず、現金やデビットカードでの支払いを優先する
- 長期的な貯蓄の習慣を身につける(例えば、収入の10%を貯金に回す)
33歳付近:ライフイベントが金銭に影響する時期
33歳付近では、結婚や出産、育児、住宅購入などの大きなライフイベントが起こりやすい時期です。これに伴い、家計の管理が大きく変化します。
金銭管理の変化
- 結婚や家庭生活に伴う出費の増加
結婚式や新生活の準備に多額の費用がかかるほか、家庭を維持するための生活費が増えます。 - 育児関連の支出
子どもが生まれると、医療費や保育料、教育費が家計を圧迫します。 - キャリア変化による収入の変動
育児休暇や時短勤務の影響で、収入が一時的に減少する場合があります。家庭と仕事の両立が課題となる時期でもあります。 - 住宅購入や引っ越し費用
マイホーム購入を検討する人も多く、ローン返済が家計に大きく影響します。
対策
- ライフイベントに備えた貯蓄計画を立てる(「結婚資金」「教育資金」など、目的別の積立)
- 家計を共有する仕組みを作り、夫婦間での金銭管理を透明化する
- 出産や育児に関する行政の補助金や助成金を調べて活用する
- 無理のない範囲で住宅ローンを組む(返済比率は年収の30%以下が目安)
37歳付近:将来への備えを意識する時期
37歳は、仕事や家庭での安定感が増す一方、老後や子どもの将来への備えを考える必要が高まる時期です。また、健康に関する支出も増える傾向にあります。
金銭管理の変化
- 教育費の負担増加
子どもが小学校高学年から中学、高校へ進むにつれて、塾や習い事の費用が増加します。 - 老後資金の準備
親の介護が現実的な課題となる一方、自分自身の老後資金の準備も必要です。 - 医療費の増加
健康診断や予防医療の費用、さらには体調不良に伴う医療費が増える時期でもあります。 - 保険の見直し
家族構成や健康状態の変化に応じて、生命保険や医療保険の内容を見直す必要があります。
対策
- 教育費や老後資金を計画的に積み立てる(学資保険やNISA、iDeCoを活用)
- 保険商品を比較し、必要な補償内容を確認する
- 健康診断や予防医療を定期的に受けることで、将来の医療費負担を軽減する
- ファイナンシャルプランナーに相談し、長期的な資産運用計画を立てる
共通する金銭管理のポイント
- 家計簿を習慣化する
収入と支出を明確にすることで、無駄遣いを防ぎ、効率的な家計運営が可能になります。 - 目的別の貯蓄を行う
結婚、教育、老後など、ライフイベントに備えた積立を行い、計画的に貯蓄を進めます。 - 家族での話し合いを重視する
夫婦や家族間で金銭に関する考えを共有し、協力して管理することで、トラブルを防ぐことができます。 - 将来を見据えた投資・運用を始める
金利が低い時代では、銀行貯金だけでなく、NISAや投資信託などの運用商品を活用して資産形成を行います。
厄年の過ごし方のヒント
厄年を穏やかに乗り越えるためには、日々の生活に少しの工夫を取り入れることが大切です。
厄除けの儀式に参加する
神社での厄払いは、日本の伝統的な方法としておすすめです。地元の神社を訪れて祈祷を受けることで、心の安定につながることも。
ポジティブな心構えを持つ
「厄年だから不幸が起こる」と考えるのではなく、「自分を見つめ直す良い機会」として捉えましょう。自己成長のきっかけとして、資格取得や趣味の時間を増やすのも良いですね。
ライフスタイルを見直す
厄年は生活習慣を見直すタイミングとも言えます。食生活、運動、睡眠の質を整えることで、健康的な毎日を送りましょう。
支え合う仲間を作る
同じように厄年を迎える友人や家族と励まし合うのも良い方法です。共有することで、気持ちが楽になることも。
厄年を前向きに捉えるために
厄年は確かに一つの節目ですが、「悪いことが起こる年」ではなく、人生を見つめ直し、整えるチャンスと考えましょう。特に女性は身体の変化と向き合う時期でもあります。心身をいたわり、ポジティブに過ごすことで厄年を乗り越え、より充実した人生を送るきっかけにしてください。
終わりに
厄年は不安を感じる年齢ではありますが、適切な心構えと行動で穏やかに過ごすことができます。この記事を参考に、厄年を安心して迎えられるよう、今から準備を始めてみてはいかがでしょうか?